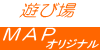 |
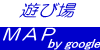 |
 |
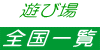 |
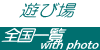 |
|
| �m�������ő�l���y���߂�V�я�̈�ł��B�������ۋ�`�Z���g���A�̋߂��ŁA���̗V�я�Ƃ��Ă͂��˂ӂ��́u�߂��p�[�N�v������܂��B���������̂��ł������ƂP�������Ղ�Ƃ����قǃ{�����[���͂Ȃ��̂ō��킹�Ă��ł�������Ƃ����Ǝv���܂��B INAX�̑̌����W���{�݂Ń^�C�����g�������̂Â���̌������ǂ낾����邱�Ƃ��ł��i�\��v�j�A�܂��^�C���̗��j�����ق���t�Õ֊�̓W�������w���邱�Ƃ��ł��܂��B ����ǂ낾�̓I���W�i�����@�ň�ʂ̂ǂ낾�̍������Ⴂ�܂��B�悭�m���Ă�����͔̂��Ɏ�Ԃ����Ԃ�������܂���ˁB�ł��A�����̓D���͂킸��1���ԂŊ������܂��I�i�������A�P�T��1�����Ŗ������Ƃ����߂��܂������j�B�r��������Ɨ͂͂��邱�Ƃ�����܂����A��r�I�N�ł��ȒP�ɍ�邱�Ƃ��ł���̂ł������߂ł��B ���Ȃ݂Ɂu�~���[�W�A���V���b�v�v�A���X�g�����u�s�b�c�F���A�@���E�t�H���i�[�`�F�v�A�����đ̌��݂̂̕��i�������w�́~�j�͓��ٗ��͕s�v�B�Ȃ̂ł����E�E�E�����ƃ`�P�b�g���m�F�����̂́u���E�̃^�C�������فv�����ł����B�Ă������炽�܂��܂Ȃ̂��Ȃ��`(^^�U |
|
|
|
�z�e���\��͂����炩�� |
|||||||||||||||||
|
| �̌��ꗗ�i���y�H�[�@�܂��́@�y�E�ǂ�فj�B���̑̌��̑��ɂ��G�߃C�x���g������܂��B |
| ���U�C�N�A�[�g | 10cm�~10cm�@�@1,200�~ | �^�C���G�t�� | 15cm�~15cm�@�@�@800�~ | ���v�G�t���̌� | 15cm�~15cm�@�@2,050�~ |
| 15cm�~15cm�@�@1,500�~ | 20cm�~20cm�@�@1,000�~ | 20cm�~20cm�@2,250�~ | |||
| 20cm�~20cm�@�@2,000�~ | 5cm�~5cm�@4���@�@1,000�~ | ����ǂ낾�� | 1�@�@800�~ | ||
| �f�R���U�C�N | 15cm�~15cm�@�@2,500�~ | �v�`�g�C���G�t���̌� | 1�i������13cm�j�@�@1,500�~ | ���邿�т��� | �i�����j1�@�@800�~ |
| �y�̃p�X�e�� | �i�����j6�F�Z�b�g�@�@800�~ |
| �����ԏ� �L���ė]�T������̂ł����E�E�E ���i�Ɏ{�݂����Ƀ}�b�`���Ă��邽�߁A�ǂ���Ɍ������Ă����̂���u�l�����Ⴂ�܂����B ���̒n�}���Q�l�ɂ��Ă��������ˁB |
| �l�`�o 6�c�̌���������܂��B���̒��ő̌��{�݂́u�y�E�ǂ��فv�Ɓu���y�H�[�v�B �̌��{�ݗ��p�����Ȃ���ꗿ�͂���܂��� ����Ƃ��Ă����E�̃^�C�������ق����ł��\���̂悤�ȋC������ |
 |
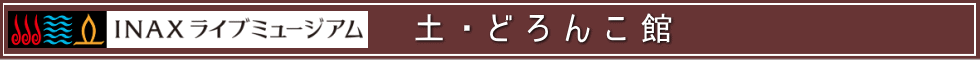
����ǂ낾���i�\�j
|
| ����J�n �^���ɂ���ɂ͗��̎�̂Ђ���Ȃ��Ȃ��ł��˂��ˁB�ł����ꂾ�Ƒ傫�Șc�݂͒����Ȃ��̂ŁA���̒����͋����̊ʂ���ł��邮����̗͂ł܂킵�č��̂ł��B ���ꂪ�|�C���g�B�͂����ꂷ����Ƃ��ɏ��������Ď��Ԃ������Ȃ��Ȃ�܂��B�B�B�B |
�������l�q
| �F�Â� �^���ɂȂ����牻�ςǂ���g���ĐF�����܂��B ���ڐF���ʂ�̂ł͂Ȃ��A��̂Ђ�ɉ��ςǂ���悹�čL���A�����������ēh��A������ƕς������@�Ȃ�ł��B |
| ���� ��ԍ����F��h��I�����ǂ낾�B�����Ă����r�Ŗ����܂��B�r�Ŗ����ƔS�y�̗��q�����ꂢ�ɕ��сA�������˂���悤�ɂȂ邩��s�J�s�J�Ɍ����ł� �������� �Ƃ肠�����̌��͂����܂ŁB1�T��1��1�x��ł�����ƍX�Ɍ���悤�ɂȂ�܂��B |
| ���� �O���A�����Ƃ��ɓy���g����������A�������݂̂���W�����B ��K�͓W�����ɂȂ��Ă��܂����A�K�i��K�i���ɂ����ԂȂǁA�����Ɋy�����H�v������܂��B�̌����I������猚���T�������܂��傤 |
| �g�C�� �g�C���̃f�U�C�����f���炵���I �q�ǂ��̍��͂����C��g�C�����^�C�����Ɠc�ɂۂ��Č��������̂ł����B�B�B�B �g��������Ȃ�ł��ˁB �Ƃ��Ă��|�b�v�œc�ɂۂ��ǂ��납�����I��������B�����݂������܂���ˁB�����˃^�C�����ā� ���Ȃ݂ɍ����j�q�g�C���ʼnE�����q�g�C���ł��B |
|||||||
| �S�y���̕��� 16��قǂ̔���̃��t�g�ɂ͐���̎���Ă��������o������������܂��B�����o�����J����Ƃ��낢��Ȏ��_���猩���u�y�v�̐��E���l�ߍ��܂�Ă��܂��B �J���邾���ł��y�����̂ł��Д`���Ă݂Ă��������B �y�̕W�{�A��G��A�a������ǂ낾�A�p�X�e���̍����A�ς������A�V���A���̃A���ː����ȂǂȂǁB�{���ɂ�������̓䂪�B����Ă����ł���B |
|||||

| �̌����� ���̎{�݂ɓW���͂���܂���B�̌�������p�Ƃ����Ă����ꏊ�ł��B ���������̌������f�R���U�C�N�͗\�B�\����Ȃ��̂̓t�H�g�t���[����N���b�v�Ȃǂ̃A�C�e�������U�C�N�^�C���ŏ���̌��̂݁B 10�F00�C13�F00�C15�F00��1��3��ł��B |
| �u�����j���[�i������j �@���U�C�N�A�[�g�̌� �A�f�R���U�C�N�̌��i�̌������̂͂����j �B�^�C���G�t���̌� �C���v�a�t���̌� �D�v�`�g�C���G�t���̌� |
 |
| �A�C�e���I�� �܂����߂�̂�������邩�I�ł���ނ����肷���ĂȂ��Ȃ������܂�Ȃ�(^^�U �T���v���������Ă���̂ŁA�C�ɓ��������̂�^�����銴���őI�ׂ������� �Ƃ������ƂŁA�����邪�I�̌��̓f�R���U�C�N�I |
| �A�C�e���I�� ���ɂǂ̃^�C����\��̂��A�ǂ�ȕ��Ƀf�R���[�V�������邩�Z���N�g���܂��B����܂����Ԃ�������܂��B �E�͐F���{�B�����ƌ��Ă���Ǝg���Ă���^�C���̐F���킩��Ȃ��Ȃ��ł���� |
| �g�I�� ���������I�т܂��B���͍��B����Ȃ��悤�Ƀ}�X�L���O���Ă���܂��B ���C�A�E�g �^�C�������u���Ă����܂��B�u���Ă݂ď��߂đS�̂��킩��̂ŁA���x�����s���낵�ĕ��ׂ邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��� |
| �^�C�����Ђ�����Ԃ��B�ؘg�{���h��h��B�ؘg��킹�A�ォ��}���� ������Ɛ��I�ŃV�r�A�ȍ�ƂȂ̂ŁA�X�^�b�t����Ƃ��Ă���܂��B |
�^�C�����є����������� �ׂ�����ƁB�ӊO�ɂ���Ă����̂ł��� |
|||
| �ڒn������ �ڒn�̓X�^�b�t���悹�Ă���܂� �ڒn���� �w����g���ĐL���Ȃ��璚�J�ɑS�̂L���Ȃ���ڒn�����܂��B |
| �@���Ƃ聕�����@�d�グ�Ƀf�R���[�V������ �����������X�|���W���g���Ėڒn���y���ӂ��Ƃ�h���C���[�Ŋ��������܂��B�Ō�Ƀf�R���[�V�����f�ނɃ{���h�����^�C���Ɏ��������ł��B���������i�ł� |
|||

| �L�� ���̎{�݂��L���ł����A�����Ɗm�F����̂͂��������ł����B�܂��L���̉��l������̂�������������(^^�U �s�b�c�F���A�@���E�t�H���i�[�`�F �C�^���A���̐d�q�ŏĂ��s�U��H�ׂ邱�Ƃ��ł��郌�X�g����������܂� |
|||
| �����ǂ̌��_ �����̓y�ǂ����������������邽�߂ɍ��ꂽ�~����̂₫���̃N���C�y�O�B ����200���{�ȏ�̃N���C�y�O�ō��ꂽ���U�C�N�͗l�Ɋ����I |
|||
| �^�C�������̂͂��܂� �e�[�}�́u�_�ƐM�̂��߂̃^�C���v�B�^�C���ƃv���W�F�N�^�[�Ő_�b�I�ȋ�Ԃ����o���Ă܂� |
�����̉F�� ���E���E�[�E��ƈڂ�ς����̌������o�����^�C�����y���߂܂��B�J���t���ȃ^�C�����Ԃ��F�Â��A���m�N���ɕς���Ă����l�q�͌�����������܂� |
||
| �l�Ԃ̂��߂� �^�C���̎n�܂� �_�ƐM�̂��߂̃^�C���͐����̂��߂̃^�C���ɕς���Ă����܂����B �^�C�����ނ����i�̂����Z�܂������w�ł��܂��B |
| ���{�̃^�C���̂͂��܂� �C�M���X�̉e�����Ȃ�����{�̃^�C�������W�B�t���A�Ō�̕����͓��{�̎l�G���C���[�W�����f�U�C���̃^�C���ň͂܂�Ă����ł���B |
|||
2�K�̓^�C���̗��j���w�ׂ�W����
| �I���G���g�̂₫���� �I���O����N�̎��チ�\�|�^�~�A�ʼn~���`�̂₫���́i�N���C�y�O�j���G�W�v�g�ł͐F�̃^�C��������Ă��������ł��B ���{���Ɠꕶ����ł����B�B�B�B���E�͐����ł��˂� |
| �C�X���[���̃^�C�� 7���I�̃A���r�A�������N�_�ɂ��ĒZ���ԂōL�܂����C�X���[��������������^�C���̓W���R�[�i�[ �_�ւ̐M�̋C�������������w�͗l�̃^�C���������I |
| �X�y�C���̃^�C�� �X�y�C���̊X�͍����A���n���u���{�a�ɑ�\�����C�X���[���̌|�p�E������F�Z���c���Ă��� �܂��C�^���A�̃}�W�����J�̉e�����A���n���ʂ̐}�����`���ꂽ�}�W�����J�^�C�������܂ꂽ�����ł� �C�M���X�i���j�A�I�����_�i�E�j�̃^�C���� |
| ���{�̃^�C�� �n���Ȍ������������{�ł̓^�C���̂悤�ȌJ��Ԃ��̑�������肱�͖̂����ȍ~�ƒx�������ł��B�ł����̌㔭�W�������݂Ɏ����������ł� �����̃^�C�� ����A����̐��t����͒��ߓ��A���[���b�p�Ől�C�������������ł� |
| �~���[�W�A���V���b�v �^�C���֘A�̃O�b�Y���R�قǂ���܂� �^�C�����f�U�C�������O�b�Y���Ă��܂蕁�i���|�������ƂȂ��̂ŁA���݂₰�Ƃ��Ă����������A�����B |
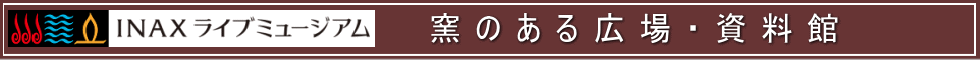
| �y�ǂ��Ă��Ă����吳����̗q�ƌ����A���˂�ۑ������������J���Ă��܂��B����1�K�ɂ͓y�ǂ�����̂ɗp����ꂽ����E�@�B�ނ̓W���A2�K�ɂ͓��{�̃g�C�������̉A�Ɣ��Ŕ������������ꂽ���t�Õ֊��W�����Ă��܂��B | ||
| ������ ���{�ŌË��̌Ã��[���� �����K�����̉����W�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B�悭�݂�Ƃ������{�݂̐����悠���ł���B ����`�A����������Ɛ������ڗ��H�v�������Ă������悤�ȁE�E�E |
| 1���ځu�y�ǁv ����������ʂ��Ă݂܂����B�h��������ł��Ȃ��݂̓y�ǂł����A���͑S���������Ȃ��Ȃ�܂����B�����q�ǂ��̍��͌����̂ł����A�ŋߌ����L��������܂���B 2���ځu�������v �R���̐ΒY������ꏊ�B��̌�����ΒY��������������A���̌�����͔R�����������������悤�ɍ���Ă��܂��B�Ă����傤�ŗq�̉��x�����Ă�����ł��� 4���ځu�̂������v �Ή��������錊�ł��B |
|||
| �y�ǂ��ł���܂� �y�ǂ���邽�߂Ɏg�����H��A�@�B�Ȃǂ̓W���A�p�l������������܂����B �����[�������͓̂����̎ʐ^�B ��������吳����Ȃ̂ł��傤���B�f�p�ȍ�ƈ����f���Ă��܂����A�d���ȊO�̐����͂ǂ�Ȋ����������̂ł��傤�ˁB |
| 2�K�� ���t�Õ֊�W��������܂��B ���x�e�p���ȁH�]�ˏ�{�ۂ̃g�C���A�]�ˎ���̋����g�C���A��������̗m���̌����֏��Ȃǂ̃��f���̓W��������܂����B ��̒����Ƀg�C��������E�E�E���ゾ�ƈ�a������܂��ˁB����ȃg�C�����Ɨ��������Ȃ��ėp�������Ȃ�����(^^�U |
| ���t�Õ֊� �Ɣ��̎�荇�킹�͐��ŃI�V�����A�Ƃ������Ƃő嗬�s����������ɂ͓����퐻�̕֊�ɂ��u�Ɣ��v�̑���������悤�ɂȂ��������ł��B �܂��召�֊킪�����͗l�ŃZ�b�g�֊�Ƃ��Ďg���Ă��܂����B |
| 1972�N����2005�N�܂ł�33�N�Ԃɓn����ۂɎg���Ă����q�����w�ł��܂��B�����ł́u�V�hNS�r���v�u���������r���i���É��j�v�u�_�ːŊցv�u�����������v�Ȃǂ̓��{�e�n�̌����̊O���^�C�������Ă��܂����B | |||||

| �e���R�b�^ �f�Ă̏Ă����Ō��z����Ƃ��ĊO�ǂ��������e���R�b�^�B 1930�N�O��ɑS�������ւ������{���\����e���R�b�^�R���N�V�����������O�ɓW�����Ă��܂� |
| �鍑�z�e�����{�قƃ��C�g | ���É��s���� | ����c���� | ������w��ȉȊw������ | ���l���w�Z | �鍑�z�e���@�� |
| �N�\ �ɓސ�����INA��INAX�ƕς���Ă����l�q�A����Ɠ����ɔ��\�������i���킩��N�\��W�� |
| �e���R�b�^�p�[�N �M�d�ȃe���R�b�^���A�{���̎p�ł���A�ǖʂɎ��t������ԂŌ��邱�Ƃ��ł���B 1937�N�Ɉɓސ����i��̂h�m�`�w�j�����삵���u���l���≮�{�فv�̃e���R�b�^���܂߁A13�̃e���R�b�^���̌��z�ʐ^�ƂƂ��ɎŐ��̍L��ɓW�����Ă��܂� |
| ����{���� | ���z��� | �����Ȓ��� | �y�R�[ | ��J������� |
| ���l���≮�{�� | �哯�����r�� | �����ΖȍH�� | ���É���s���� | ���������� | ���ɗp���q��w�b�q����� |
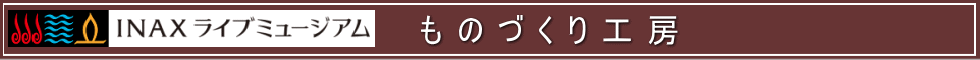
| ���̂Â���̓`����Z�p���A���i�⎑����ʂ��ďЉ��R�[�i�[ �^�C���������W�̗��j�����n���JAXA�̒n��ϑ��q���u�������v�ŎB�e���^�C���ɏĂ������R�[�i�[ �E�E�E�Ȃ��Ă��K�v���B�ʂɂ�������(^^�U �܂��H��̗l�q��`�����Ƃ��ł��܂� |
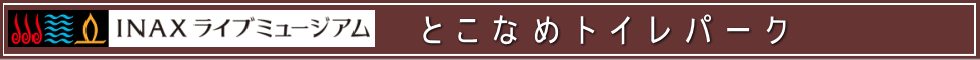
| 1988�N10���Ɋ������������B����A�^�C�����g���������ȃg�C��������_�͕]���ł�����̂́A�����Ƃ��Ă̋@�\�͂قڂȂ��A����قǐ�������Ă��Ȃ��_��AINAX���C�u�~���[�W�A���̗��ɂ����ċC�����ɂ����Ƃ����_�͌����Ƃ��Ă͒v���I�B�̂͗V��������̂��낤���H | |||
